

FAQ


FAQ
トレーラーハウスの購入・設置を検討される際に、多くのお客様から寄せられる質問と回答をまとめました。
もし、ご希望の回答が見つからない場合は、こちらのお問い合わせフォームやお電話( 0120-368-904 )でお気軽にご相談ください。
スタッフが丁寧に対応させていただきます。
基礎がなく、タイヤの分地面から上がっているので、シロアリ被害が少なくなります。
トレーラーハウスは住宅ではなく車扱いなので住宅ローンを組むことはできませんが、
事業用であればご利用可能です。
個人の場合は、カーローンやフリーロンもご利用可能ですが、よくご検討の上、ご利用いただくことをお勧めします。
そのため、トレーラーハウスとして連結することは不可です。
ただし、弊社の場合はユニットハウスも製造しているため、建築確認許可を取れば移動可能なユニットハウスとして使うことは可能です。
ご相談ください。
下水道管が前面道路まで布設されていれば下水管に接続。なければ浄化槽に接続します。
一般住宅と変わりありませんが、接続口が簡易的に取り外せるものである必要があります。
但し防火地域によって、消防法では建築物でなくても防火対象物として、準耐火構造にしていなければならない、と規定されています。 また、当社では安全、安心を第一に考えており、その観点から、用途によって防火基準を決めております。詳しくは当社までお聞きください。
トレーラーハウスを利用した旅館業法のホテル営業許可を取得する場合、いずれも設置場所を所管する
(1) 建築行政
(2) 消防署
(3) 保健所の許可
がからんできます。
まず、建築行政で建築物に該当しないトレーラーハウスの種類、設置方法を相談され、建築物でないことを確認します。
その後、消防署で防火対象物の防火基準、ホテル営業に伴う安全義務を確認し、保健所に相談してください。
しかし、弊社の場合はユニットハウスの製造もしておりますので、ご相談ください。
トレーラーハウスが特定の場所に定置され、土地側の電気・水道・ガス等を接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
建築基準法第2条第1号で規定する建築物としてトレーラーハウスを使用する場合は、基本的にはタイヤを外し、基礎を作り建築確認を申請する必要があります。
建築基準法第2条第1号で規定する建築物でないものとしてトレーラーハウスを使用する場合は、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」にある建築物に該当しない条件を満たさなければなりません。
建築物に該当しない条件
随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること。
土地側のライフラインとの接続が工具を使用しないで着脱できること。
適法に公道を走れること。
事前に建築確認申請を行わず、建築物に該当しない条件も遵守していない場合、その時点で建築基準法の適用を受け、違法建築物として見られます。
又使用中に随時かつ任意に移動できない設置になった場合も、その時点で違法建築物になってしまいます。
トレーラーハウスと道路運送車両法
日本建築行政会議「車両を利用した工作物」で決められている、適法に公道を走れること、即ち法律に基づき公道を走行する為の法律が道路運送車両法に該当します。
道路運送車両法第4条に、自動車は自動車登録ファイル(車検証)に登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない、と有り車検のないものは公道を走行することは禁じられています。
車検を取得する要件として、安全基準、日本の道路を走れる為の自動車の大きさが決められており、その大きさを規定するものが保安基準第2条の制限になります。
今までトレーラーハウスの法律が整備されていない為、違法に公道を走っておりましたが、平成24年12月国土交通省自動車局において「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」が施行されたことで、車検取得ができなくても個別に基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可が取得出きる自動車として追加されました。
この制度改正により、法的に見たトレーラーハウスの分類は下記の通りになります。
道路運送車両法によるトレーラーハウスの区分
保安基準第2条の制限以内のトレーラーハウス
車幅2500mm以下 全長12000mm以下 高さ3800mm以下の場合は車検を取得できる大きさの為、公道を走行する場合、安全基準を満たし車検を取得して運行しなければならない。
保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウス
車幅2500mm、全長12000mm、高さ3800mmを超えたトレーラーハウスは、運輸局で基準緩和の認定を受け、道路局で特殊車両通行許可を取得して公道を走行しなければならない。
建築基準法でいう建築物に該当しない前提として、自動車であることが必須条件になります。
車検のないトレーラーハウスは基準緩和の認定を受け、特殊車両通行許可を取得して公道を走行しなければ、日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の車両に該当しませんので、くれぐれもご注意ください。
トレーラーハウスと都市計画法
都市計画法による開発行為とは、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に対するものであって、建築物に該当しない場合はこの法律は適用されません。
法的に言えば 建築物の許可されない土地であっても建築物でない為、都市計画法の適用を受けず、トレーラーハウスを設置することは何ら問題ない、と解釈されますが、当社としては、これを脱法行為に該当する、と考えます。
このような、規制のある土地として定められている地域は、理由があって定められている為、「公共の用に供する場合」もしくはそれに準ずる場合を除いては、脱法行為と判断せざるを得ず、今後はっきりした法律を作っていかなければならないと考えます。
但し、自治体により、減価償却税がかかる場合があります。 又、車検の付いているものは取得時に自動車税、重量税、自動車取得税がかかります。 年度ごとに自動車税がかかります。 車検更新時には重量税が必要になります。
但し、自治体の判断によって、トレーラーハウスの中でも建築物に該当するもの、建築物に該当しないものがあります。 設置場所を管轄する建築行政、もしくは当社へ事前にご相談ください。 トレーラーハウスを購入する前に必ずご相談下さい。
但し、市街化調整区域という建築規制のある地域内で、建築物に該当しないから問題なく、認可されるものではありません。
まずは、運送事業者の車庫が環境上市街地から郊外に追いやられている状況の中で、事業を行うに当たっての安全点検等が、同一敷地内で出来ない現実があり、違法と言われるプレハブ等で現実的な安全点検を行っても何らかの事故が起きた場合、違法な事務所を使用している為、処罰の対象になってしまいます。
建築物でないトレーラーハウスは法的には市街化調整区域でも置くことは出来ますが、当社ではむやみにそれを推し進めることはしていません。
まずは事業所認可が安全点検という世の中の為になるということ。
又、同一敷地内に違法建築物があった場合、それを撤去し今後についても違法を行わず、コンプライアンスを遵守し、安全点検を心がける運送事業者の皆様の為には協力をしていきたいと思います。
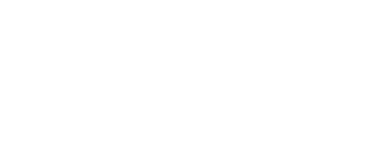
「まずは設置ができるか知りたい」「実際にトレーラーハウスを見てみたい」
「資料がほしい」などご要望別に選べるお問合せの窓口をご用意しています。

実物を見てみたい方はこちら。

「こんなこと聞いてしまってもいいのかな?」と思ってしまうようなことでも遠慮なくお問い合わせください。

完成見学会や相談会を行っています。

以下のボタンからお申し込み後、すぐにメールで送付いたします。